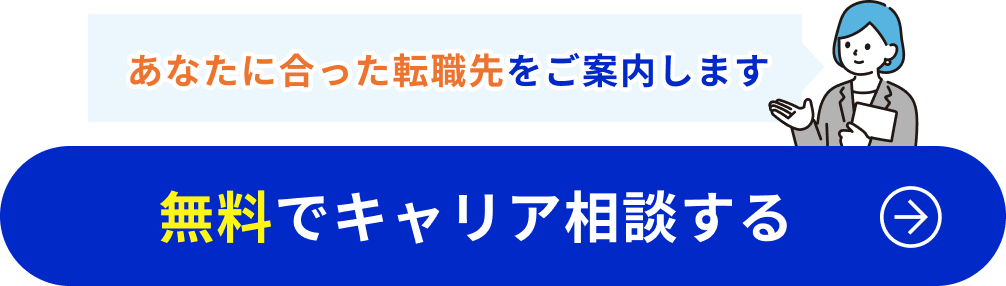「退職日の決め方が分からない」「損したくない」20代のあなたへ。社会保険料・賞与・有給休暇など、自己都合退職で最適な「退職日」を選ぶための全手順をツナグバが徹底解説します。
「退職日って、どうやって決めるのが正解なんだろう?」「社会保険料やボーナスで損したくないけど、一体いつにすればいいの?」
もしあなたが今、そんな疑問や不安を抱えている20代なら、この記事はあなたのためのものです。自己都合退職を考えているけれど、退職日の決め方で失敗したくないあなたへ。
社会保険料の負担、賞与の受け取り、有給休暇の消化など、お金の面で損をせず、かつ円満に退職するための賢い退職スケジュールの立て方を、20代の転職をサポートするツナグバが法的根拠や客観的なデータを交えながら、分かりやすく解説します。
この記事を最後まで読めば、退職日に関するあらゆる不安が解消され、自信を持って次のキャリアへスムーズに進むための具体的な知識が得られるでしょう。最適な退職日を選び、後悔のない新しい一歩を踏み出しましょう。
退職日で変わる「社会保険料」の負担額と賢い調整方法
退職日をいつに設定するかで、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)の負担額が変わることをご存知でしょうか。社会保険料は月単位で計算されるため、一般的に以下の点が重要です。
社会保険料(健康保険や厚生年金)は、その月の月末に会社に在籍しているかどうかで支払い義務が決まります。月末まで会社にいれば、その月の保険料を支払う必要があります。
一方で、「月の途中で退職すれば保険料はかからない」と言われることもありますが、実際は会社のルールによっては日割りで保険料が引かれることもあるため、必ずしもゼロになるとは限りません。
そのため、退職日を決めるときは、「月末かどうか」だけで判断せず、事前に会社へ確認しておくことが大切です。
「賞与」や「退職金」を損しない!退職日の見極め方と確認事項
賞与(ボーナス)や退職金の支給タイミングを逃さないことも、退職日の決め方において重要な要素です。多くの企業では、賞与の支給条件として「支給日に在籍していること」や「特定の評価期間に在籍していること」を就業規則で定めています。そのため、退職日が基準日より早いと、受け取れるはずだった賞与を逃すリスクがあります。
厚生労働省の「毎月勤労統計調査」によると、多くの企業で賞与の支給時期は夏期(6~7月)と年末(12月)に集中する傾向があります。これらの時期を考慮し、賞与支給日以降に退職日を設定することで、確実に賞与を受け取ることが可能です。
退職金についても同様で、その支給条件は企業の就業規則や退職金規程によって詳細が定められています。勤続年数によって支給額が変わる場合も多いため、自身の勤続年数と照らし合わせ、最も有利なタイミングを見極めることが賢明です。これらの金銭的な要素で損をしないためにも、必ず事前に就業規則を確認するか、人事担当者に直接問い合わせておくことをお勧めします。
円満退職とスムーズな転職を実現する「退職スケジュール」の立て方
自己都合退職を円滑に進め、次の転職に繋げるためには、会社に迷惑をかけずに円満に退職し、自身の転職活動もスムーズに進めるための計画的な退職スケジュールが不可欠です。
1. 法的な通知期間と就業規則に合わせた退職申し出
まず、退職の意思を伝えるタイミングです。法律(民法第627条第1項)では「雇用期間の定めのない労働者」の場合、退職日の2週間前までに通知すれば退職が成立すると定められています。しかし、多くの企業では就業規則で「退職の1ヶ月前まで」「3ヶ月前まで」など、より長い通知期間が定められているのが実情です。円満退職を目指すのであれば、この就業規則を尊重し、余裕を持った期間で退職を申し出ることが推奨されます。
2. 有給休暇の消化計画と業務引き継ぎのバランス
残っている有給休暇を退職日までにすべて消化することは、労働者の正当な権利です。労働基準法により、会社は原則として有給休暇の取得を拒否できません。未消化の有給休暇を残すのは、非常にもったいないことです。
計画的に有給休暇を消化するためには、事前に上司や人事担当者と相談し、スケジュールを調整しておくことが大切です。例えば、退職希望日から逆算し、残りの有給休暇日数を含めた最終出勤日を設定します。
この際、スムーズな業務引き継ぎを同時に進めることが円満退職の鍵です。
- 自分の業務内容や担当プロジェクトをリストアップし、資料やデータを整理しましょう。
- 後任者が決まっている場合は、OJT(On-the-Job Training)形式で実際の業務を体験させながら、不明点や疑問点をその場で解決するよう心がけましょう。
- 引き継ぎの進捗状況を上司と共有し、最終出勤日までに全ての業務が後任者に引き継がれていることを確認します。
丁寧な引き継ぎは、あなたのプロ意識を示すとともに、退職後に問い合わせが来るリスクを減らし、良好な人間関係を維持することに繋がります。
3. 次の職場入社日からの逆算と退職日の最終決定
次の職場への入社日が決まっている場合、そこから逆算して現在の会社の退職日を設定することが最も効率的です。これにより、収入の空白期間を最小限に抑え、生活面での不安を軽減できます。
例えば、次の職場の入社日が4月1日で、現職の有給休暇が10日残っている場合、3月20日までに業務を完了させ、その後有給休暇を消化して3月31日を退職日とするスケジュールが理想的です。転職エージェントを利用している場合、エージェントが現職と新しい職場との間のスケジュール調整をサポートしてくれるため、非常にスムーズです。
まとめ:賢い退職スケジュールで20代未経験の転職を成功させよう!
自己都合退職における退職日の決め方は、単に会社を辞める日を決めるだけでなく、社会保険料、賞与、有給休暇など、金銭面や次のキャリアに大きく影響する重要な要素です。月末退職が必ずしも最適とは限らず、ご自身の状況や会社の就業規則、そして次の職場の入社日などを総合的に考慮し、最も賢い退職スケジュールを立てることが、損をしない円満退職とスムーズな未経験転職を成功させる鍵となります。
特に20代での未経験転職は、人生における大きな転機です。不安を感じることもあるかもしれませんが、正しい知識と計画があれば、自信を持って次のステップに進むことができます。
あなたの「理想のキャリア」をツナグバが一緒に見つけます!
「退職日の決め方が不安…」「未経験からの転職、何から始めればいい?」と感じている20代のあなた。
私たちツナグバは、20代など若手の未経験転職に特化した転職エージェントです。あなたの不安や疑問を丁寧にヒアリングし、退職から転職までのあらゆるステップをサポートします。
退職日に関する具体的なアドバイス、円満退職のための会社への伝え方、あなたの強みを活かせる未経験歓迎の求人紹介、履歴書・職務経歴書の添削、面接対策など、あなたの転職活動を二人三脚で徹底的にサポートします。
「未経験だから」と諦めるのはもったいない!あなたの可能性を広げる一歩を、私たちツナグバと一緒に踏み出しませんか?まずはお気軽にご相談ください。
この記事の監修

海老名 信行
取締役/COO
株式会社ツナグバ
大学卒業後、株式会社ギャプライズにてWebマーケティング支援の営業として、大企業を中心とした新規顧客開拓とリレーション構築に従事。
次に、株式会社サイファーポイントに取締役/営業責任者として参画。新規顧客開拓、DXコンサルティング、WEBマーケティング支援を経験。
プロフィール紹介

 適職診断を受けてみる
適職診断を受けてみる