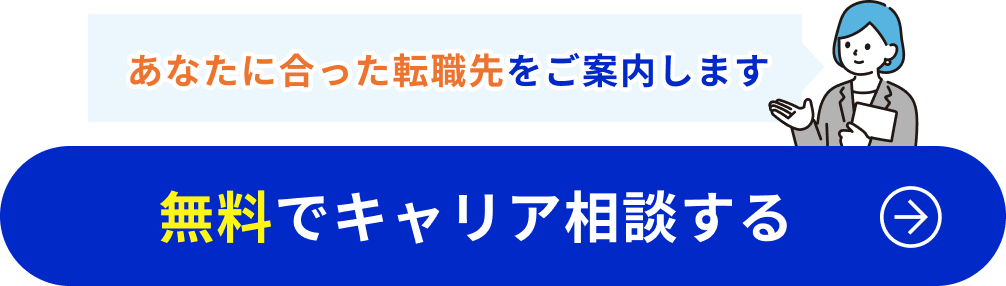「退職日って自分で決められるの?」「会社に勝手に決められたらどうしよう…」と不安な方へ。
この記事では、自己都合退職における退職日の決定権が誰にあるのか、法的な根拠と具体的な事例をもとに分かりやすく解説します。
退職をスムーズに進めたい20代のあなたに向けて、円満に辞めるための具体的な手順も紹介。ツナグバが退職から転職までしっかりサポートしますので、ぜひ参考にしてください。
自己都合退職における退職日の決定権は誰にあるのか?
自己都合退職の場合、退職の意思表示をした日から2週間が経過すれば、労働者は法的に退職できると民法第627条第1項により定められています。この規定は、期間の定めがない雇用契約(いわゆる正社員など)に適用されます。つまり、退職日は労働者自身が退職の意思を示した日から起算して2週間後以降であれば、労働者の都合で決定することが可能です。
たとえ就業規則や労働契約書に「退職は○日前までに申し出ること」などと記されていても、これは原則として社内ルールであり、法的強制力をもって民法を超えることはできません。したがって、会社が労働者の同意なく退職日を一方的に決定したり、退職自体を拒否したりすることは、基本的に法的に認められません。
ただし、円満な退職を目指すうえでは、引き継ぎや業務調整の観点から会社と事前に話し合い、双方納得のうえで退職日を決めるのが望ましい対応です。
退職日をめぐるトラブル防止!会社都合・合意退職の正しい知識
一方で、会社が退職日を提示できる例外的な状況も存在します。
- 会社都合退職の場合:会社の都合で退職を余儀なくされる場合(整理解雇、倒産など)は、会社側が退職日を指定することがあります。
- 期間の定めのある労働契約(契約社員・派遣社員など): 契約期間満了をもって退職する場合は、契約期間の終了日が退職日となります。ただし、やむを得ない事情がある場合は、契約期間中でも退職を申し出ることが可能です(民法第626条)。
- 合意解約の場合:労働者と会社、双方が話し合い、退職日について合意するケースです。この場合、双方の意思表示によって退職日が決定されるため、会社が一方的に押し付けることはできません。例えば、業務の引き継ぎ期間を考慮し、労働者と会社が納得できる退職日を設定することが多いです。
いずれのケースにおいても、会社側が一方的に退職日を押し付けることはできず、労働者との合意形成が不可欠であることを理解しておく必要があります。
退職届の正しい書き方とトラブル回避のポイント
退職日を巡るトラブルを避けるためには、退職届の正しい書き方と提出時の注意点を理解しておくことが重要です。特に20代の場合、初めての退職で戸惑うことも多いため、具体的なルールと手順を確認しておきましょう。
退職届には主に「作成日」「提出日」「退職希望日」の3つの日付を記載します。
- 作成日:退職届を作成した日付です。
- 提出日:退職届を会社に提出する日付です。直属の上司に口頭で退職の意思を伝えた後に提出するのがスムーズです。
- 退職希望日:あなたが退職を希望する具体的な日付です。民法に基づけば、提出日から2週間後以降の日付を設定できますが、円満退職を目指す場合は、業務の引き継ぎ期間などを考慮し、会社側と調整した日付を記載するのが望ましいです。
日付表記は西暦・和暦どちらでも問題ありませんが、社内文書で統一された形式がある場合はそれに従いましょう。 書類内で表記を揃えることがポイントです。
また、一度提出した退職届の撤回は、基本的に「会社が承認前である場合」や「会社との合意がある場合」に限られます。撤回が難しいケースも多いため、退職届提出は慎重に行う必要があります。
円満退職の具体的な手順と20代の転職成功術
自己都合退職を円滑に進め、次の転職に繋げるためには、計画的な手順が不可欠です。
- 直属の上司への相談:まずは口頭で退職の意思と希望日を伝えます。メールではなく、対面で誠意をもって伝えることが円満退職の第一歩です。
- 退職届の提出と退職日の最終確認:口頭での相談後、正式に退職届を提出します。提出時にはコピーを手元に残しておくと安心です。その後、会社側と退職日を最終的に確認し、合意形成を目指しましょう。
- 有給休暇の消化と業務引き継ぎ:残りの有給休暇は労働者の権利として取得可能です。有給消化を含めた退職日を会社と相談し、スムーズな業務引き継ぎの計画を立てましょう。業務内容のリストアップ、資料整理、後任者への丁寧なレクチャーは、退職後のトラブルを防ぐ上で極めて重要です。
20代での転職は、未経験の分野へ挑戦する大きなチャンスです。自己都合退職は悪ではなく、あなたのキャリアをより良い方向へ進めるための前向きな選択です。
まとめ:自己都合退職の不安解消へ
自己都合退職における退職日の決定権は、最終的に労働者にあります。
民法第627条により、退職の意思表示をした日から2週間が経過すれば退職は法的に成立しますが、円滑な業務引き継ぎや良好な人間関係を維持するためには、会社との協議と合意形成が望ましいです。もし話し合いが難航し、会社が一方的な退職日を主張する場合は、労働基準監督署や弁護士への相談も有効な解決策となります。
退職のルールを理解し、冷静に対処することが、トラブルを避け、あなたの新しい未来をスムーズにスタートさせるための鍵です。私たちツナグバは、20代など若手の未経験転職に特化したキャリア支援サービスを提供しています。「退職手続きが不安」「未経験の転職、何から始めればいいか分からない」と感じている方は、ぜひツナグバにご相談ください。
この記事の監修

海老名 信行
取締役/COO
株式会社ツナグバ
大学卒業後、株式会社ギャプライズにてWebマーケティング支援の営業として、大企業を中心とした新規顧客開拓とリレーション構築に従事。
次に、株式会社サイファーポイントに取締役/営業責任者として参画。新規顧客開拓、DXコンサルティング、WEBマーケティング支援を経験。
プロフィール紹介

 適職診断を受けてみる
適職診断を受けてみる